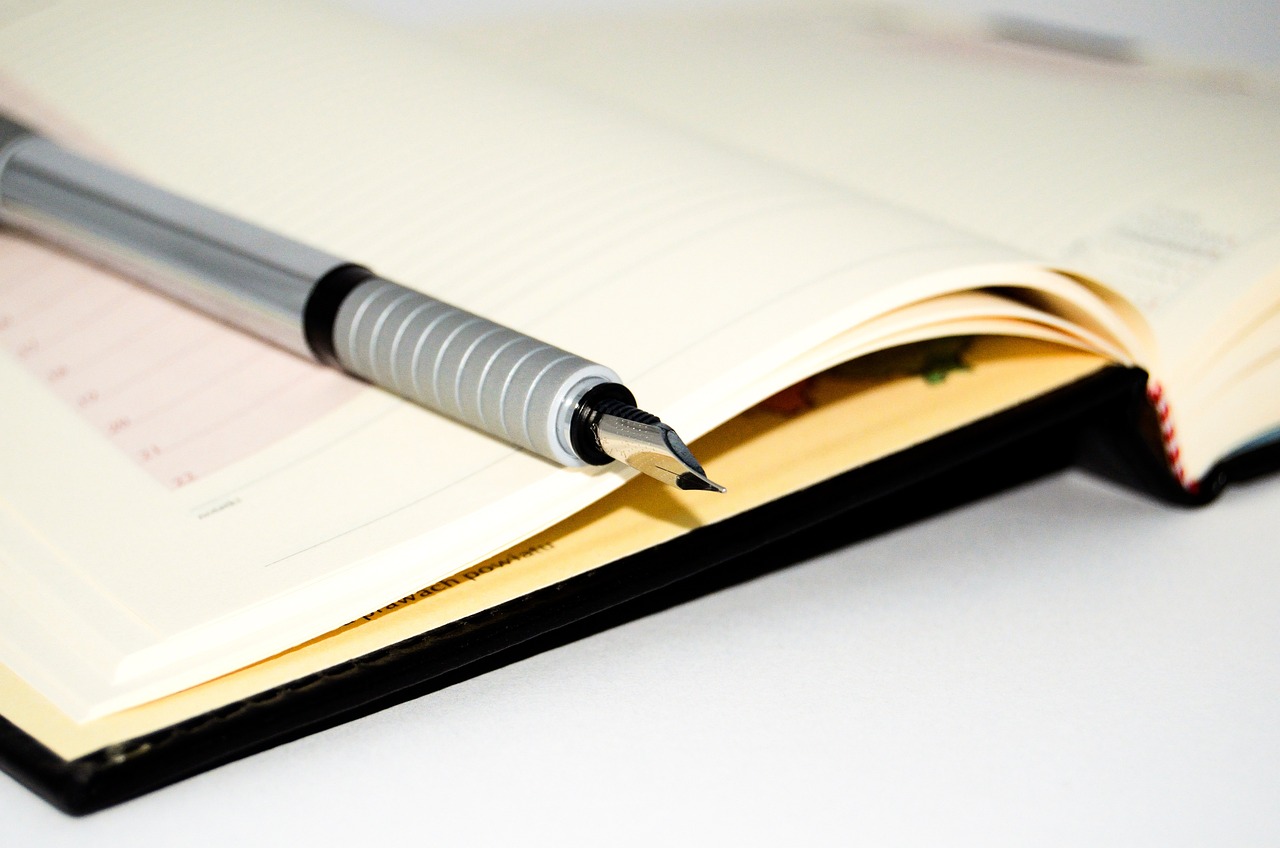「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。 資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、そ …
投稿者アーカイブ: office-bit
相談費用はいくらですか?
初回は60分無料にて承ります。A4一枚の簡単なアンケートにご協力ください。 2回目以降は30分8,000円にて承りますが、その後ご依頼を頂いた場合は相談料は報酬に充当致します。
出張・テレビ会議には対応していますか?
どちらも対応可能です。 出張の場合は、基本的には出張費を頂戴いたしますのでご相談ください(目安:半日3万円~)。ご紹介の場合、出張費は頂戴しておりません。
既に認知症ですが契約できますか?
判断能力の程度により、契約が出来る場合もございますので、まずはご相談ください。 全く意思疎通が出来ない場合は成年後見人の手続きとなります。 この場合は遺言書を作成することも出来なくなってしまいますので、認知症になってしま …
家族信託に掛かる費用を全て教えてください
大きく分けると、①契約時に掛かる費用、②継続的に掛かる費用に分かれます。 ①は業務案内に詳細がございますのでこちらをご覧ください。 ②は主に受託者への報酬を設定した場合と、受託者の業務を司法書士や税理士に外注する場合の費 …
信託契約書は公正証書にすることが必要ですか
必須ではありませんが、した方がよい場合もあります。 法的には基本的に信託契約書は公正証書にする必要はありません。 しかし、金融機関で受託者名義で口座を開設したい場合、公正証書で信託契約書を作成していないと口座開設に応じて …
不動産の登記は必須ですか
後々不動産を売却したりする場合には必須です。 不動産の権利の登記(所有者が誰であるか等)は基本的には義務ではなく、権利です。つまり、してもしなくてもよいということになっています。 しかし、登記をしていると第三者に自分が所 …
不動産を信託しますが、お金もした方がいいでしょうか
物件により変わってきます。 不動産の維持管理にお金が掛かる場合、お金もセットで信託しないと支払いに困ってしまいます。 しかし、アパートや賃貸マンションなどの収益を生む不動産の場合、その収益から支払いができるということもあ …
家族信託するか成年後見をするかで迷っています
その時点での認知症等の有無とコスト、そもそもの目的で判断することになります。 目的とは、例えば家とアパートの維持管理や売却がしたいという場合です。 まず、既に認知症になってしまっている場合は成年後見を申し立てるしかありま …
亡くなった方の契約している保険を調べるには?
亡くなった方が契約している保険を調べるには、主に3つの方法があります。 1つ目は、故人の遺品や通帳、クレジットカードの明細などを調べて、保険会社や保険証券、ご契約内容のお知らせなどの書類を探す方法です。 2つ目は、一般社 …